宅録ナレーターに挑戦したいけれど、何から始めればいいのか分からない。
機材のこと、録音環境のこと、そもそも自分の声で仕事ができるのか…。
そんな不安や疑問を感じる方は少なくないと思います。
実を言うと、私もスタートしたときはまったくの初心者で、不安ばかりが先に立っていました。
けれど一つずつクリアしていくうちに、今では宅録で安定してナレーションの仕事を受けるようになりました。
この記事では、これから宅録ナレーターを目指す方に向けて、初心者でも安心して始められるよう、基礎から丁寧に説明していきます。
自分の体験を交えながら、なるべく分かりやすく、具体的にお伝えします。
宅録ナレーターとは?

まずは、「宅録ナレーター」という働き方について、基本的なことを押さえておきましょう。
自宅で完結するナレーション業
宅録ナレーターとは、録音スタジオに出向くことなく、自宅にある機材と環境を使ってナレーションを収録し、音声データとして納品する仕事を指します。
最近は企業や個人からのナレーション需要が増え、宅録のスキルがあると副業やフリーランスとして大きな強みになります。
私が宅録を始めたきっかけは、コロナ禍で外に出られなくなったことでした。
声の仕事は好きだけどスタジオに行けない…そんな状況で見つけたのが宅録でした。
始めてみると、自分のペースで仕事ができて、家事や育児とも両立しやすく、思った以上に自分に合っていたと感じました。
活躍できるジャンルは意外と多い
ナレーションといってもジャンルはさまざまです。
企業のPR動画、商品紹介、eラーニングの教材、電話の自動音声、YouTube動画、電子書籍の読み上げ、ゲームのキャラクターボイスなど、用途によって求められる声も違います。
宅録ナレーターとして活動するには、自分の声がどのジャンルに合っているのかを見つけるのが最初の一歩になります。
YouTube向けナレーションの特徴
YouTube動画に使われるナレーションは、通常のナレーションとは少し異なる特徴を持っています。
どのような点に注意して取り組むべきかをまず理解することが重要です。
ナレーションの目的は視聴者の引き込み
YouTube向けのナレーションは、ただ情報を伝えるだけでなく、視聴者を引き込み、興味を持たせる役割を果たします。
例えば、商品レビュー動画や解説動画の場合、視聴者が動画を最後まで見てくれるように、リズムよく、感情を込めた読み方が求められます。
私は最初、YouTube向けのナレーションをやる際に、ただの情報を伝える読み方ではなく、視聴者に「もっと見たい」と思わせるような声を意識しました。
ナレーションを通して、動画に命を吹き込むことが重要だと感じました。
視聴者の集中を引き出す声の使い分け
YouTubeの視聴者は、短時間で情報を得ることを好みます。
そのため、ナレーションにもテンポ感が求められます。
単調な読み方では視聴者の集中力が途切れてしまうため、感情やトーンを上手に使い分ける必要があります。
具体的には、解説の部分は落ち着いたトーンでわかりやすく伝え、興奮が必要な場面では声を高めにしてエネルギッシュに読んだりすることが大切です。
こうした声の使い分けが、視聴者の注意を引きつけるカギになります。
宅録に必要な機材とその選び方
「ナレーターってプロ用の高価な機材を揃えないとダメなの?」と思うかもしれませんが、実はそんなことはありません。
最低限のクオリティがあれば、十分に仕事は始められます。
マイク
最も重要なのがマイクです。
USBマイクとXLRマイク(オーディオインターフェースに接続するタイプ)の2種類がありますが、本格的にやるならXLRタイプのコンデンサーマイクをおすすめします。
私も最初は安価なUSBマイクから始めました。
慣れてきたタイミングで、定番のコンデンサーマイクに買い替えたところ、声のクリアさが段違いで、案件の評価も上がりました。
オーディオインターフェースとモニターヘッドホン
コンデンサーマイクを使うなら、オーディオインターフェースも必要です。
音の出力だけでなく、ノイズを抑える役割もあるので、録音品質にこだわるなら必須アイテムです。
私が使っているのは初心者向けでも評価の高い製品で、3年以上トラブルなく使えています。
ヘッドホンは、自分の録音を正確に聞き返すための重要な道具です。
音漏れしにくく、長時間でも耳が疲れにくいタイプを選ぶと快適に作業できます。
録音環境づくりのポイント
自宅収録では、「いかに雑音や反響を抑えるか」が勝負です。
完璧な防音室がなくても工夫次第で乗り切れます。
雑音対策は生活スタイルから見直す
私の家はマンションの1階で、外の音や上階の生活音が気になることが多かったです。
そのため、録音時間は深夜や早朝など静かな時間に限定したり、冷蔵庫や換気扇などの音を一時的に止めるようにしました。
地味な工夫ですが、これだけで録音のクオリティが安定しました。
反響を抑えるための身近なアイテム
壁に布を掛けたり、押し入れを簡易ブースにしたり、吸音材を使ったり…いろいろ試しました。
結果、最も効果的だったのは、使っていないクローゼットの中を録音スペースにしたことです。
狭い空間で音が反響しにくく、毛布を周囲に吊るすことで簡易的な吸音効果も得られました。
プロフィールとサンプル音声の作り方
録音環境が整ったら、次はプロフィールとサンプル音声の準備です。
ここで手を抜いてしまうと、せっかくのスキルも伝わりません。
自分の強みを明確に伝えるプロフィール
私は、初めてココナラで出品したとき、「ナレーションします」だけのシンプルな紹介文を載せていました。
でも、それでは誰にも刺さらず、まったく反応がありませんでした。
そこで、自分の得意ジャンル、声の雰囲気、過去の実績、納期対応などを丁寧に書いたところ、問い合わせが増えました。
「親しみやすい声で、柔らかく伝えるのが得意です」「即日納品可能、修正にも柔軟に対応します」など、相手がイメージしやすい言葉を使うことが大切だと実感しました。
サンプル音声は“相手の耳”を意識して
最初に作ったサンプルは、自分で書いた原稿を淡々と読んだものでした。
ところが、それでは表現の幅が伝わらず、チャンスを逃してしまいました。
今では、「企業向け」「CM風」「落ち着いた読み」「元気系」など、目的別に複数の音声を用意しています。
ココナラでは複数のサンプルを載せられるので、ジャンルごとに分けておくと、依頼する側にも親切です。
実際に仕事を取るための行動
準備が整ったら、あとは行動あるのみです。待っているだけではなかなか仕事は来ません。
ココナラやクラウドソーシングで地道に実績作り
私が最初に使ったのはココナラでした。
出品後しばらく反応がなかったのですが、価格を少し下げ、サービス説明を丁寧にしたことで、ようやく初めての依頼が来ました。
その一件目がすごく嬉しかったのを、今でもよく覚えています。
少しずつ実績がついてくると、リピートや紹介も増えていきました。
大事なのは「丁寧に、確実に」対応することだと思います。
SNSでの発信も効果あり
宅録の様子や音声サンプルをSNSに投稿することで、同業者やクライアントとのつながりができることもあります。
定期的に投稿していると、「〇〇の雰囲気が好きです、お願いできますか?」といったダイレクトな問い合わせをもらえることもあります。
スキルを伸ばし続けることが大切
ナレーションの仕事は、ただ声を出すだけではありません。
伝える力、感情表現、滑舌、すべてが大切です。
ナレーションは“聞かせる技術”
実際の案件では、ただ台本を読めばいいわけではなく、聞き手の心に届く読み方が求められます。
私は定期的にボイストレーニングの本を読んだり、発声の練習音源を使ってトレーニングしています。
少しずつでも続けていれば、確実に変化が見えてきます。
フィードバックから学ぶ姿勢
納品後にフィードバックをもらえることがあります。
最初はダメ出しに落ち込むこともありましたが、素直に受け止めて改善すると、次に活かせるようになります。
「気持ちのこもった読み方になってきましたね」と言ってもらえたときは、本当に嬉しかったです。
まとめ
宅録ナレーターは、誰でも始められるけれど、簡単ではない仕事でもあります。
ただ、自分の声を仕事にできるという喜びは、何にも代えがたいものがあります。
「声に自信がない」「機材が不安」「仕事が取れるか心配」…そんな思いがあっても、一歩を踏み出せば、少しずつ道が見えてきます。
私自身、迷いながら進んできました。でも今、宅録ナレーターという働き方に心から満足しています。
この記事が、宅録ナレーターを始めたいと考えている方の背中を、少しでも押すことができたなら嬉しいです。
まずはできるところから、ゆっくりでいいので始めてみてくださいね。
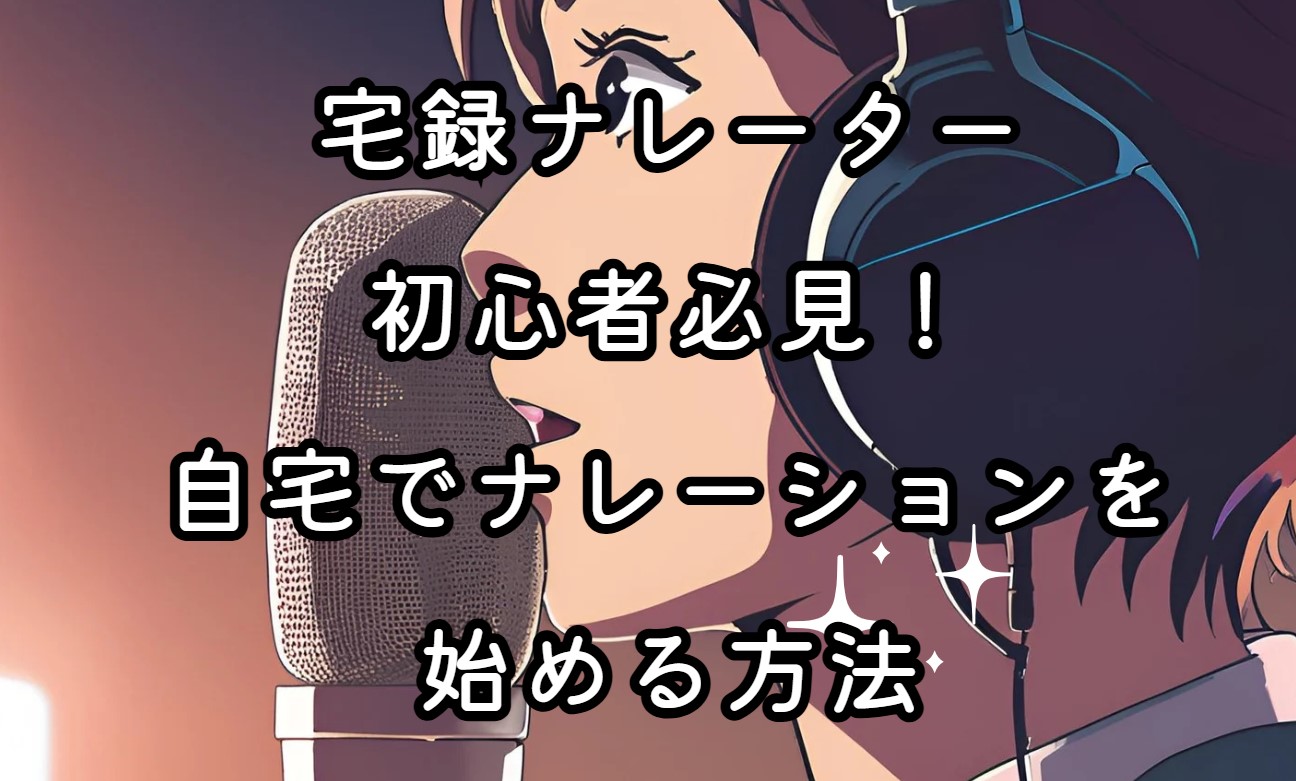
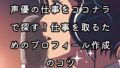
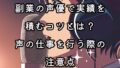
コメント