今回は、ちょっと見過ごせないニュースを取り上げます。
岩屋毅外相が中国との経済対話の場で、精米の輸入拡大を求めたという件。
一見「経済協力の話かな」と思いきや、SNSでは「ちょっと待って」と疑問の声が相次いでいます。
何があったのか?――日中ハイレベル経済対話での発言
『岩屋氏はまた、日本産牛肉の輸入再開、精米の輸入拡大も改めて要請した。』
中国の米を日本人が食べるなんてどこに書いてあるの。 https://t.co/nGgvcnuOUm pic.twitter.com/dx6yawUyCJ
— isklove2ver. (@EDK9R2A84M21D75) March 22, 2025
3月22日、東京で行われた「日中ハイレベル経済対話」。
この中で、岩屋外相が中国側に対して日本産の精米の輸入を拡大してほしいと要請したことが報じられました。
中国では検疫制度が厳しく、日本の米は簡単には輸出できない状況が続いています。
今回の要請は、そうした規制を緩和し、日本の農産物輸出を促進する狙いがあると見られます。
でも、今って…日本のコメ、足りてないよね?
ここで疑問が湧いてくるのが、まさにこのタイミング。
というのも、ここ最近「米が高い」「店でなかなか手に入らない」といった声が、各地で聞かれるようになっています。
天候不順や生産量の減少などもあり、日本では“ちょっとした米不足”のような状況になっているんです。
そんな中で、「日本の米をもっと中国に売りたい」という話が出たことで、SNSでは批判的な反応が相次ぎました。
SNSの反応:「その前に日本人に食べさせて」
ニュースが出た直後から、SNSでは次のような声が飛び交いました。
- 「米が高くて困ってるのに、なぜ中国に輸出?」
- 「国民の食卓より、中国への営業を優先するの?」
- 「農家の利益も大事だけど、まず国民の生活を守ってよ」
特に多かったのが、「まず国民が安心して食べられる状況を整えるべきでは?」という意見。
政府の方針が“海外重視”に見えることへの不信感が、こうした声につながっているようです。
農業振興と国民生活のバランスは?
もちろん、農産物の輸出を拡大していくことは、農家の収益確保や地方経済の活性化にとって重要な政策です。
しかし、その一方で「国内で足りていない状況で輸出を進めるのはどうなの?」という素朴な疑問も、決して無視できないものです。
外交の現場での交渉と、私たちの生活の実感には、時にズレがある。
今回の件は、まさにそのギャップが浮き彫りになった例かもしれません。
今後どうなる?そして私たちはどう考える?
中国側がすぐに精米の輸入を受け入れるかどうかは不透明ですし、実際に輸出が増えるとしても、制度の見直しや時間が必要です。
ただ、政府がどこに目を向けているのか、何を優先しているのかは、私たちが注視していくべきポイントです。
大事なのは、農業支援と国民の食生活のバランスをどう取るか。
この問題を一時の「炎上」で終わらせず、もっと深く考えるきっかけにしたいところです。

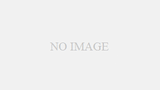
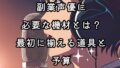
コメント